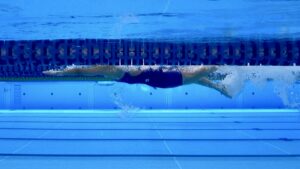スポーツのパフォーマンスにおいて、自分の身体を素早くコントロールすることは重要な要素です。
プライオメトリック・トレーニングは、そのような能力を向上させるために効果的であるトレーニング方法です。
今記事を「書いておかなきゃ!」って思わされたのは、担当アスリートからの一言。そのときの想いを綴った投稿を掲載しておきます↓
アスリートのトレーニングって色んなことに想像をめぐらせなくちゃいけない。
— 山﨑 裕太(Yamazaki Yuta) (@hari_sports_YY) May 22, 2024
水泳選手なら泳ぐことが優先。
だけど、泳いでばかりではすぐに頭打ち。
だから、筋トレもする。
だけど、重いもの持ち上げてるだけじゃすぐに頭打ち。
だから、ジャンプもする。
だけど、飛んでばかりじゃすぐに頭打ち。… pic.twitter.com/E4JUNYay6u
アスリートのトレーニングって、管理すべき「変数」が多いのよね。ただ数字を管理するだけじゃなく、目の前にいる生身の人間を相手にするわけなので、個体差もある。どれをどこまで数字に反映させるべきか?研究による知見と経験値との行ったり来たりで最後は「えい、やっ!」って組むことが多くなります。だからこそ、担当しているアスリートへ説明ができるようにしておきたい。そんなスタンスで仕事に向き合ってます。
プライオメトリックトレーニングの効果
✅プライオメトリックトレーニングは、「ジャンプ力、敏捷性(アジリティ)、スプリント能力、最大筋力、筋持久力、バランス能力」など、多様な競技のアスリートにとって様々な向上効果をもたらします。
(2024:Javier Sanchez-Sanchezら)(2024:Nuannuan Dengら)(2023:Alex Ojeda-Aravenaら)
プライオメトリックジャンプトレーニング(PJT)は、身体フィットネス、特にジャンプ、スプリント速度、筋力、持久力に小さな改善をもたらすことを発見しました。PJTプログラムの実施期間は中央値で8.5週間でした。ほとんどの研究で、身体フィットネスの向上の背後にある神経機械的メカニズムは明らかにされていません。したがって、最適なPJTの量を明らかにするために、さらなる研究が必要です。さらに、PJTを含む包括的な多次元長期トレーニングプログラムの効果を明らかにするために、12週間以上の長期研究が必要です。最後に、PJT後の身体フィットネス向上の背後にあるメカニズムを明らかにするために、今後の研究が求められます。
(2021:Silvia Soleら)
プライオメトリックトレーニングのプログラミング
プライオメトリックトレーニングの効果を最大限に引き出すため、そしてアスリートを必要以上にトレーニングさせないためにも、適切なプログラミングが重要です。プログラミングには、以下の要素を考慮する必要があります。
- 期待する効果を認識する
- 動きの習熟度
- トレーニングの頻度
- トレーニングの種類
- ジャンプの回数
- レスト
プライオメトリックトレーニングの頻度
週あたりに、何回のセッションを取り入れるか?
異なる頻度のプライオメトリックトレーニング(PT)が若年男性バレーボール選手のジャンプパフォーマンス、スプリント速度、サーブ速度に与える影響を分析しました。結果、週1回(EG1)および週2回(EG2)のPTセッションは、統制されたトレーニングボリュームの下で、同等にこれらのパフォーマンスを改善することが分かりました。つまり、プレシーズン(8週間)において、週1回のPTセッションは週2回のセッションと同様の効果を持つことが示されました。
(2023:Jordan Hernandez-Martinezら)
トレーニングの種類
水平方向へのジャンプか?垂直方向へのジャンプか?
カウンタームーブメントジャンプのように「垂直方向」へ飛ぶトレーニングか、立ち幅跳びのように「水平方向」へ飛ぶトレーニングかによってジャンプ力向上効果に対する議論があるようです。
水平方向プライオメトリックトレーニング(水平方向PT)は、垂直パフォーマンスの向上において、少なくとも垂直方向プライオメトリックトレーニング(垂直方向PT)と同等に効果的であり、水平パフォーマンスの向上においては優れています。これは、水平方向PTがスポーツにおける多方向のパフォーマンスを向上させるためのより効率的な方法である可能性を示唆しています。
(2021:Jason Moranら)
この研究の目的は、垂直(VPT)、水平(HPT)、および垂直と水平を組み合わせた(V+HPT)プライオメトリックトレーニングが成人男性サッカー選手のスプリント、ジャンプ、および方向転換(COD)パフォーマンスに与える影響を比較することでした。ジャンプ力と方向転換能力のパフォーマンスは向上しましたが、直線的なスプリントパフォーマンスには大きな変化が見られなかった。これらのテスト全体で変化を引き出すのに他の方法が優れているということはなく、方向特異的な適応パターンは明らかではありませんでした。
(2024:Jason Moranら)
この研究の目的は、若いサッカー選手の爆発的パフォーマンスとスプリント力-速度プロファイルにおけるプライオメトリックトレーニングの水平および垂直方向の影響を比較することです。水平および垂直のプライオメトリックトレーニングは、若いサッカー選手のジャンプおよびスプリントにおける垂直および水平パフォーマンスを向上させるために使用できます。しかし、水平のプライオメトリックトレーニングは、垂直ジャンプの質を同様に向上させつつ、水平の弾道運動においてより大きな改善をもたらす可能性があります。
(2024:Florian Norgeot , Alexandre Fouré)
ウエイトを持つジャンプと持たない(自体重)ジャンプの比較
この研究の目的は、加重ジャンプスクワットトレーニング(WJST)と自体重スクワットジャンプトレーニング(BMSJT)の効果を比較することでした。48人の健康なサッカー選手がオフシーズンのランダム化比較試験に参加しました。8週間のトレーニング介入の前後に、下肢除脂肪量、筋力、方向転換、スプリント、ジャンプなどが測定されました。 下肢除脂肪量の増加はWJSTでBMSJTよりも大きく、アジリティテスト、10 mおよび30 mスプリントはWJSTでのみ改善され、スクワットジャンプはBMSJTでWJSTよりも改善されました。 スクワット1RMとピークトルクの増加は両グループで類似しています。 WJSTでは、BMSJTに比べて着地フェーズでの慣性が増加し、特定の筋肉構造に伸張性収縮負荷による適応が生じました。 WJSTでの方向転換能力の改善は、増加した伸張負荷によって生成されるブレーキング能力の向上と関連している可能性があります。
(2018:Coratella, Giuseppeら)
ドロップジャンプの高さの違い
男子青少年サッカー選手での実験。ドロップジャンプ40cmグループは、ドロップジャンプ20cmグループと比較してに関して、カウンタームーブメントジャンプ・方向転換能力・2400mタイムトライアルなどのパフォーマンステストにおいて、わずかに大きな改善効果が観察されました。
(2019:Rodrigo Ramirez-Campilloら)
▶︎ドロップジャンプで着地するときの深さは、膝のポジションに影響を与える可能性があるので注意深く見守りましょう。
参考(2018:Sofia Ryman Augustssonら)
ジャンプの総数
1週間あたりにどのくらいプライオメトリックジャンプを実施したら効果的なのか?また、最低でも実施すべき回数などは示されているのか?
この研究は、シーズン中の8週間(週2回)の低回数と高回数のプライオメトリックトレーニングが前思春期の男子サッカー選手の体力に与える影響を評価し比較しました。結果、低回数と高回数の両グループでスプリントタイム、方向転換能力、ジャンプ能力が同様に向上しました。時間効率を考慮すると、運動能力向上のために低回数が推奨されます。
(2017:Helmi Chaabene, Yassine Negra)
上記の研究では、低回数グループは1週目に50-60回のジャンプから始まり、8週目には110-120回のジャンプ回数へ漸増していきました。高回数グループは1週目に110-120回のジャンプから始まり、8週目には200-220回のジャンプ回数へ漸増していきました。
とはいえ、なんか指標くれ。って声があるんで私がテキトーに書いておくと…
水泳選手だったら、週に2回以下のプライオメトリクスを実施する場合、週50回以下からスタートして、8週目に100回を目指す。くらいのビビりながら増やしていくくらいで良いかと。
取り組む人の性別も年齢も競技歴も動作の習熟度も何も無いなかでのテキトーな指標なので、悪しからず。
年齢(成熟度)による効果の違い
プライオメトリック・トレーニングに取り組んで、効果を期待するには「年齢」も関係あるんじゃないの?
11,028件の研究が特定され、最終的に11件(744名参加)がメタアナリシスの対象となりました。PJTはPHV前後の若者の筋力、スプリント速度、ジャンプ距離、RSI、SSPを改善し、これらの効果は成熟度に関係なく見られました。しかし、サンプルサイズの小ささなどの方法論上の問題があるため、将来の研究では骨年齢やタナー段階などの成熟度の測定と報告が重要です。
(2023:Rodrigo Ramirez-Campilloら)
水中でのプライオメトリックトレーニングもオススメだよ!

私見まとめ
当たり前なのですが、トレーニングにおける変数(期間/頻度/種目/回数など)を決定していくためには、目の前の選手が「いまどの段階」なのか?というのを見ていきカスタマイズしていくしかないよね。
これはプライオメトリックトレーニングに限らず、競技の練習も、ウエイトを用いた筋力トレーニングも同じ。
例えば、「週2回も1回も同様の向上効果であった!」という研究報告があったとして、あなたの目の前のアスリートにも当てはまるか?というのは立ち止まって検討したほうが良いでしょう。
週1回で十分な刺激量であれば、しばらく増やす必要はない。週2回やらなきゃいけないと考えられる習熟度だとしても、メインである競技練習のジャマをしてしまうようなら時期を考えなきゃいかん。
なので、アスリートを担当しているトレーニング指導者は「競技指導者」とコミュニケーションが取れる人であることが望ましいよねぇ。スポットでの外部指導だったりならば要らないかもだけど。
最後は本記事の本題であるプライオメトリックから話題が逸れたけど、定期的に書いておきたくなっちゃうのよw